2020年5月19日放送の【 連続テレビ小説「エール」】37話のネタバレです。
連続テレビ小説「エール」はNHKで放送しているドラマです。
現在は(2020年6月現在)NHKオンデマンドでも視聴可能です。
テレビまたはNHKオンデマンドが見れない方やこのドラマに興味のある方はこの記事をご覧になってください。
あらすじ
早稲田大学応援部の団員たちに、慶応の「若き血」に勝つ曲をとお願いされた応援歌「紺碧(ぺき)の空」の作曲依頼。曲を書いてみようとレコード会社のサロンで構想を練る裕一に、木枯(野田洋次郎)は歌手の山藤太郎(柿澤勇人)を紹介する。山藤は、慶応の応援団に「若き血」の歌唱指導をした張本人だった! なんとかありきたりではない曲を書こうと努力する裕一(窪田正孝)だったが、なかなか書けず…。
-
37話ネタバレ
エール (37)「紺碧(ぺき)の空」
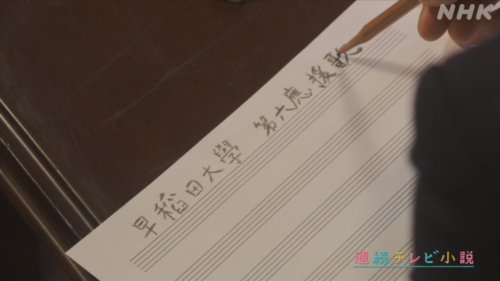
木枯「お待たせ。 君に ちゃんと紹介しておきたいと思って。 山藤太郎さん」
山藤「改めまして 山藤です。」
裕一「あっ。 古山裕一です。 あっ 木枯君とは同期で… 差は もう ついちゃったんですけど…。」
山藤「木枯さんは あなたには とても 才能があると おっしゃってましたよ。」
裕一「お世辞ですよ。」
木枯「僕は お世辞なんか言わない。 君の曲は 山藤さんに きっと合うよ。 いつか 是非一緒にやってほしいな。」
裕一「あ… ありがとう。」
山藤「あれ? これ…。」
裕一「ああ… あの… 早稲田の応援歌 頼まれまして。 慶應の あの『若き血』に必ず勝てって 言われてます。」

山藤「フフ…。」
裕一「どうしました?」
山藤「『若き血』は 僕が塾生時代に生まれたんです。」
裕一「えっ?」
山藤「応援団に歌唱指導したのは僕なんです。」
裕一「えっ… 応援団だったんですか!?」
山藤「いえいえ…。 歌の指導を頼まれたんです。 その時 僕は まだ2年生なのに 上級生に対して 何度も何度も 違うと 歌わせたあげく…。」
回想
山藤「何回言ったら分かるんだ。 ただ 大声出したって 気持ちは伝わらないんだ! あなたたちは 母校を愛してないのか!?」
上級生「うるせえ~! 調子に乗るな。 俺はお前より慶應を愛してる! この大学を 何よりも誰よりも 俺は愛してる!」

山藤「それです。」
上級生「はあ?」
山藤「今のあなたの叫びこそ 『若き血』です。」
回想終了
山藤「『若き血』が応援歌になって以来 我が慶應義塾は早稲田に連戦連勝」です。 勝つのは… 容易ではないですよ。」
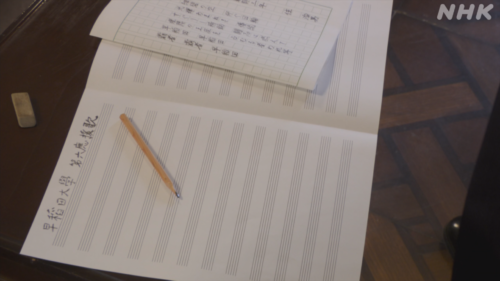
う~ん… 勝ち負け以前の問題です。
古山家
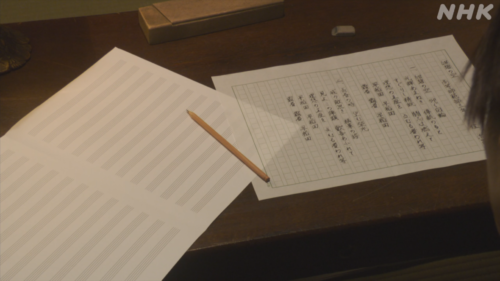
あれ? まだ書けてない。え~?
裕一「あ~ ありがとう。」
音「進まんの?」
裕一「う~ん…。 前半は シューベルトのイメージで いけそうなんだけどね 最後がもう全く浮かばない。」
音「『覇者 覇者』の部分?」
裕一「応援歌ってさ 迫力が大事だと思うんだけど『は』の発音って弱いでしょ?」
音「そうね。 『か』とかなら いいのかな?」

裕一「『勝つ!』とか こう… 『かっ飛ばせ~』とか…。 提案してみようか。」
音「うん… 頑張って。」
裕一「ありがとう。 『勝~つ!』『かっ飛ばせ~』。」
喫茶店 バンブー
田中「なかです! この歌詞は完璧ですけん。」
裕一「そうですか…。」
田中「特に この『覇者 覇者』は 慶應ば圧倒する気持ちが出とって 譲れんとです!」

裕一「そ… そう… はい 分かりました。 はい。」
田中「お願いします!」
裕一「はい… はい… お願いされました。」
田中「失礼します!」
裕一「はい どうも。 ご苦労さまです。」
保「ありがとうございました。」

保「お代わりは?」
裕一「あっ お願いします。」
保「困ってるね~。 書けないの?」
裕一「あ~… 応援歌って ほら ある一定の形 あるじゃにですか。 どうしても それに引っ張られて ありきたりになっちまうんです。」
保「ありきたりじゃ まずいの?」
裕一「いや そりゃ… そりゃ どうせ 作んなら 違うもん作りたいじゃないですか。」
保「そっか… そうだよね。 僕も 毎日 同じコーヒーを作ることに 疑問を持つことがある。」
裕一「いや… コーヒーは…。」
保「えっ 何?」

裕一「いや… その味が飲みたくて来てるわけで 毎回違ってたら… 困りますよ。」
保「裕一君が書けないのはさ 自分の音楽を 作ろうとしてるからじゃないかな?僕が コーヒーをブレンドする時に 考えるのは お客さんの顔なわけ。 これを飲んだら どんな反応するかなとか。」
古山家
裕一「意味分かんないよ! 僕が 曲 作んのに 何で自分の音楽 作っちゃいけないの? だったら ほかに頼んでも同じ ってことになんない?」

裕一「マスター 客商売だから こびないと やっていけないかもしれないけど 僕たちの世界じゃ 意味ないよね!? ねえ そう思わない?」
音「難しいよね。」
裕一「いや 人のまねして歌えって言われて どう思う? ありきたりの歌が分りやすいからって 安易でしょ?」
音「私は まだ基礎やっとる段階だから よく分からんけど…。」
裕一「何?」
音「廿日市さんも言ってた。 裕一さんの音楽は 西洋音楽に こだわっとるって。」
裕一「そ… そりゃ… そりゃ 僕 西洋音楽で 音楽 学んだだもん しかたない。」
音「そうなんだけど… 作ってくる曲が… 作ってくる曲が…。」
裕一「何? 言って。 聞いときたい。」
音「怒らん?」
裕一「うん… 僕 冷静だよ。 言って。」
音「『鼻につく」って。」

音「普通に盛り上がればいいメロディーも 何か… こざかしい知識をひけらかして 曲を台なしにしとるって。」

音「怒った…。 でも言っときたかったの。 1年間 1枚も レコードになっとらんのは事実だし 何か変えんと まずいと思う。」
裕一「変える? 変える? フフ… 何それ。 いや… 本当だったら 今頃 イギリスで 音楽の勉強してるはずだったのに 東京の隅っこで 応援団と大衆曲の曲 作ってんだよ?」

裕一「もう十分 変わってるよ! それでも… それでも 自分の音楽 表現しようって頑張ってんだよ!」
音「…なら このままでいいの?」
裕一「自分の音楽は捨てないよ。 捨てたら意味ないよ!」
音「もういい。 明日から ごはんは作りません。 勝手にやって下さい。」

裕一の仕事場
裕一「ん~! んっ… んっ! あ~ みんな 何なんだよ…。 僕に何を期待してんだよ! 人には得意不得意あんだろうに…。 うん…。 こうなったら…。」

裕一「これだ… これが僕だ。」



コメント