待田家
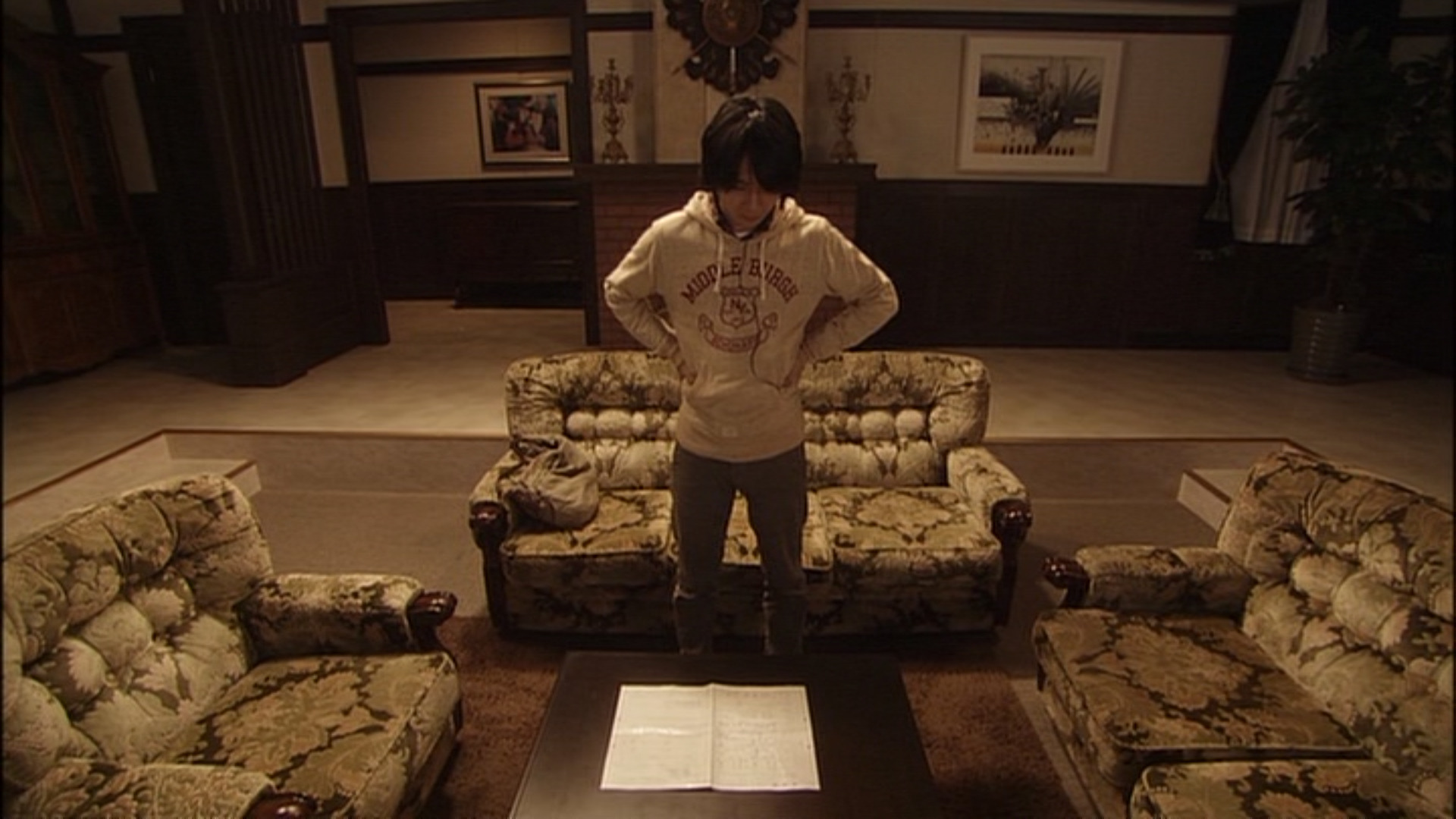
多恵子「もう うるさくって 仕事に ならないじゃないの!」
愛「え? 聞こえてました?」
多恵子「音楽じゃないわよ あんた! もう うっとうしいから もう早く出て行ってくれない? 一生彼女を支えるって決めたんでしょ?」

多恵子「だったら なんで 1番苦しい時に そばにいてあげないのよ? なんでホテル以外で仕事したら離婚するわけ? じゃあ なに? 私が弁護士やめたら あんたの母親じゃなくなっちゃうわけ?」
愛「親子と夫婦は違いますから。」
多恵子「そんなのわかってるわよ でも言わずにいられないのよ。 ついでに この前聞かれたこと 全部答えるあげるわ。 私が弁護士になったのは 男じゃなかったことにガッカリした父親を見返してやりたかったからよ!」

多恵子「あんたの父親と結婚したのは 若い頃 あの人のことを心から尊敬していたから あなたと純が生まれた時には そりゃもう 私に人生で1番 幸せな時間だった 素晴らしいことを成し遂げたって気がして自分が誇らしかったわ。 だから ”純”と”愛”なんて名前つけたんじゃないの。」
愛「お母さんがつけてくれたんですか?」
多恵子「悪い? あなたの父親は”愛”っていうのはやめた方がいいって言ったけど でも私は”愛”と書いて”いとし”と読めばいいって譲らなかった。 この子は男とか女とか そんな枠を超えた凄い子になってくれたらいいって。 以上。 わかったら とっとと出て行きなさい。」
離婚届を破り捨てる多恵子

愛「ふっ。」
多恵子「なによ?」
愛「いえ。 一生お母さんの口から そういうこ言葉が聴けると思ってなかったから。」
多恵子「え?」
愛「凄い嬉しいです。 ありがとうございます。 行ってきます。 お母さん。」

玄関
多恵子「あら?」

純「夜分遅くにすみません。 あの愛君いますか?」
多恵子「今 帰ったけど 会わなかった?」
純「え? まさか 離婚届 出しに行ったんじゃ?」
多恵子「知りたきゃ 自分で電話かけてみれば?」

純「それが 私携帯忘れちゃって あっ すみません ありがとうございました。」
多恵子「待ちなさい 私が今電話してみるから。」
純「ありがとうございます。」
リビングから携帯の着信音が聞こえる



コメント